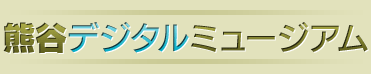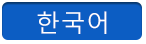田山花袋『東京近郊一日の行楽』
田山花袋(1872-1930)が、東京を中心として、日帰りまたは一泊二日の旅行をする者のために書いたガイド本『東京近郊一日の行楽』。この中に、大正4年1月17日に、小説『残雪』の題材とした上州旅行の際に妻沼を訪れ、聖天山境内の千代舛に宿泊した際のことが「妻沼の聖天祠」として書かれています。
(前略)
私は太田の呑龍の入口の前で、妻沼の方へ行く馬車を待った。「さうですな、中食する位の隙はありませう」かう馬車の親分らしいやわらか物を着た男が言ふので、私はそのすぐ前の飯屋に入って昼飯をすませた。
やがて馬車は出た。
(中略)
二里の路はさう大して遠くなかった。やがて私は利根川近くに来ていた。で、私は馬車から下ろされた。
「妻沼かえ?もう?」
「川をわたると、すぐでさ」
かう言って、馬車は妻沼の方から来た客を一人拾って、さっさと元来た路の方へと引かへして行った。顧ると、太田の金山は安蘇山群の中にぴったりとくっつくやうになって了っていた。此處で見ると、日光山群の雪が矢張その山脈の盟主をなしていた。
やがて私の前には、雪を帯びた利根川が廣く静かに展けられた。岸に残った雪に日影がきらきらと反映して、碧い碧い水の色が刺すやうに刺激した。川上には、河川工事の浚渫船が繋がれてあって、黒い煤煙がもくもくとあたりに漲り渡った。
「川上の浚渫船に立つけふり残れる雪の上になびけり」かういふ歌を私は詠んだ。それから「おく山の雪よりかけて遥かにも野になびき伏すあその村山」かういふのも出来た。
やがて聖天の森がこんもりと前に見え出して来た。「呑龍と聖天と相對す夜の寒さかな」かう言って私は独り笑った。
妻沼の聖天祠は、埼玉ではきこえた流行佛である。東京などからも講中があって、二月の節分などには非常に賑はふのが例だ。「聖天さまだけは信仰するものぢやない。屹度願が叶ふけれど、その人一代で、あとはすっかり駄目になって了ふ」などと言ふけれども、それでも聖天を祈って、家運の隆盛を来たしたものは沢山にある。
妻沼の町はさびしい田舎町だ。しかし聖天の社は宏壮を極めている。門から本堂まで一二町、境内には大きな杉の樹が茂って、昼猶暗しといふ趣がある。山門を入って本堂、そこには蝋燭が一杯上げられてあって、読経の聲が常にあたりに響いてきこえた。
私は山門の前にある料理兼業の旅館の一間に一夜すごした。其處では、「昼すぎの町をすぎ行く獅子舞の笛わが窓の紙にひびけり」だの、「宵の間はさわがれ夜はたわられてねられざりけり田舎の宿屋」などといふ歌を詠んだ。
あくる朝は早く起きて、其處等を歩いた。山門の鳩の啼声、毛糸の襟巻をして朝早く遊んでいる娘達、早くから始っている鉦と読経の聲、「子供等は早し御堂の朝明けの鳩と共にも出でて遊べり」かういふ風に私はその實景を歌にした。
其日は私は利根川に添った路を東に向って、今まで来た山を後ろにした。
今度は秩父の山の雪が私の眼を明かにした。そして二時間後には、見沼用水の利根からわかれるあたりを通って、新郷から羽生の町の方へ出て来ていた。
関東平野をめぐれる雲は、猶美しく私の周囲にあった。
今はしかし太田、妻沼、熊谷間に定期自動車が出来て一時間位で往ったり来たりすることが出来た。

『東京近郊一日の行楽』(国立国会図書館デジタルコレクション)