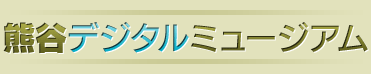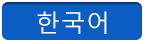川路聖謨 『島根のすさみ』
『島根のすさみ』に記載されている籠原の茶屋(しがらき茶屋)の記述を紹介します。
この日記は、天保11年(1840)、幕府勘定吟味役の川路聖謨(としあきら:1801-1868)が、佐渡奉行所の腐敗を一掃するために佐渡奉行に抜擢され、江戸から中山道を通り三国峠、寺泊を経由して佐渡に渡り、再び江戸に戻るまでの日々を記したものです。
「島根」は佐渡相川、「すさみ」は心に浮かんだあれこれということです。
天保11年(1840)7月11日に江戸を発ち、7月12日には上尾から本庄まで進んでおり、途中籠原で小休止しており、様子を記しています。
「籠原の建場にて従者の物語を聞に ここの牛房の味ことによしといふ故 障子の破よりうかがひみしに白き飯にそへて物する様いかにも味あるかことくにみゆ よつて密に申して某か如くにはせて一椀をとりよせものせしに いかにも味あり 飯二椀をものしぬこのことのなからましかは けふは飢可申によき序にそありけるされと又一笑の事也 ここにて梅ひしほのうちにはしかみを薄くきりて加たり 甚よし 作りて母上に奉るへし 紫蘇の実をも少々加へたると覚ゆる也」
籠原の茶屋で食べたごぼうが、ご飯を2杯も食べるほどおいしかったと記しています。「梅ひしお」は、梅干しで作った万能調味料です。
 |
| 竹野半兵衛1827年『諸国道中商人鑑』「志がらきノ笹屋源蔵」 |
出典
川路聖謨・川田貞夫『島根のすさみ』佐渡奉行在勤日記 東洋文庫226 1973年