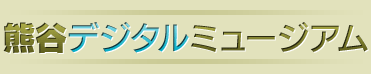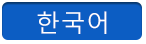石原雅次郎 『かげりゆく心』
石原雅二郎著の『かけりゆく心』:大正11年(1922)刊を紹介します。
内容は、明治44年中山道を徒歩で板橋から大阪まで歩いた際の旅行記です。板橋を出発して二日目に熊谷に到着しています。
熊谷では、「魚かつ」で熊谷住の有力者(高柳・斎藤・牛島半舟ほか)による歓迎会が開かれ、田島屋に宿泊しました。翌日は、星溪園を訪ね、竹井耕一郎と会っています。「高柳」は、素封家の高柳二郎(1872-1928)、「斎藤」は政治家で俳人の斎藤清治(紫石)(1885-1964)かもしれません。
石原雅二郎(つねじろう)(1888-1946)警察官僚・政治家・教育者
前略
「久下の長堤は権八地蔵で名高い。ここ迄来ると夕日は浅間を雲煙模糊の間に浮出さしめた。上州界の山々も右に蜿蜒として連る。荒川は昨夜の雨で水嵩増り、土手の下まで濁流が洗っている。今一息で大洪水となるところだつた。
向から大な旗をかついだ人が来る。「石原さんぢやありませんか」「ええ」と答へると「萬歳」と言つて旗をふつた。元気のいい人だ。熊谷から此處まで迎へに来たのだと言つて肩から掛けている袋の中にサイダーの瓶がコツンコツン鳴つている。
熊谷は二萬以上の人口がある。各街道の衝に当り、米穀、織物の取引が盛なところである。町も廣く、東京を出て初めて見る盛な町である。此の夜、熊谷の有力家高柳氏や斎藤氏、俳句に熱心な牛島半舟氏など十人許で盛な歓迎の宴を「魚かつ」と言ふ料理屋で開かれた。久下の土手まで大旗たてて迎に来られたのは木村氏である。皆自分のことの様に悦んで呉れられる。宴が終わつたのは夜半過。一時半頃迄かかつて通信文を綴りかけたが、思ふ通りにならぬから、廿七日朝五時に起きて書く。(於田島屋)
第二日。行程九里。計十七里強。旅費一圓也。内譯、晝食及茶代五十銭、氷に二十銭、壹銭五厘切手廿枚三十銭。
また、見出しにもあるように、明治44年には「星渓」と呼ばれていたことがわかります。
「星溪
熊谷の町に来る旅人は、忙しさうに熊谷寺を訪うでて、又過ぎ去って了ふだらう。櫻の土手に荒川の流を見る人は多いかも知れぬ。然だし、熊谷に来て、見落としてならぬものが一つある。それが廣く世に知られぬのが残念である。幸いに木村君は早朝僕をここに連れて来た。
竹の折戸を叩いて、池の一覧を乞えば、主人は快く自ら導いてくれた。庭の池に舟を浮べてこの幽景を賞する。
星溪とは水木清華荘の事である。漢源閣とも言ふ。又勝海舟は依緑書院と名付けた。その境は狭く、一私人の庭園に過ぎぬ。然しその水の湧くところ、其の清冽。其の池の幽蓬なること。眞に深山の趣がある。池は楓樹の緑に囲まれ、銀杏の影を底に寫し、竹林は擲玕戛々の響きがある。音なく湧く底まで水は清い。飽くまで澄み切って魚の噞喁するさま、水なく唯空中にかかると言ふも、決して過言では無い。
荘の主人、竹井耕一郎氏は星溪観楓記に於て、監谷青山先生の為に記して、
中央澄潭、玲瓏如鏡、岸上之物影悉蕪在水底、舟行其間、五色粉披、有魚数百、聞跫来集、出没噞喁、似楽人之楽者云々。
到底、短い通信文では、この景を寫すことは出来ぬ。竹井氏は偶然にも僕と同じく一高出身で、氏の親友とは言はるる方は皆僕の大學に於いての恩師である。もし「霜露既に下って、星溪の老樹染めて綿繍に似たる」の頃であったら、眞に天下の絶景であらう。熊本の水前寺は水を以て顕るるも、之に比ぶれば遠く及ばぬ。舟から水に一分間、手をひたせば殆ど感覚を失ふ程冷い。池には無数の鯉を放ち、赤き、黒き、白き、紫の色をしたものも居る。青銅に名工の巧を誇りしもの、■あつて水中を泳ぐか。眞に自然の美は、この星溪に奪はれ盡している。
武蔵野を旅する人よ。熊谷を過ぐる人よ。忘るる勿れ、熊谷の町には星溪の幽境あることを。荘主竹井氏は法學士である。「一朝獲病歸田」し、「逍遙至道之中自適生死外」自らこの荘に臥して再び世に出でられぬ。氏は今病癒え、専ら誌作に思をやり、悠々、「物外洗雙耳」又「枯淡作生涯」と吟じて居られる。訪づるる人があれば悦んでこの勝を萬人に許される。甞て皇后陛下の行啓があつたとは木村君の談である。又朝鮮伝来の袖振石、天柱石の珍品も蔵せられ、茶室もある。
希くは諸先生に侍して、再びこの境に遊びたいものである。舟は中央に止り、細波たたず。朝の蒸気が白く登るを見て、一杯の茶をすすり別るとき、竹井氏は監谷青山先生、筧先生に好音を傳へよと言ふ。氏の近什に、
欲寫會心趣、奈無坡老才、竹風吹月上、溪霧厭欄来、樹老棲山鳥、潭清見底苔、不知人生熱、恍似坐瑤台。
と。この一時間は恐くは中山道旅行中の最も愉快な時となるだらう。(新町へ向ふ途上、深谷小學校の歓迎に臨みて。二十七日午後三時記。)
 |
 |
| 絵葉書「熊谷割烹魚勝」明治~大正期 | 絵葉書「星溪園玉の池」明治~大正期 |
出典
石原雅次郎 1922『かけりゆく心』法制時報社