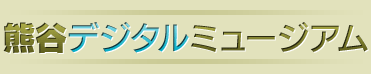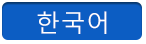長島甚助(ながしまじんすけ)(1864-1934)
長島甚助は、元治元年(1864)小八林の地主長島茂の子として生まれました。師範学校を卒業し、地元小学校教師となるが、明治28年、熊谷町の鴨田半三郎から座繰り製糸「日進館」を譲受け実業の道に進みます。
明治29年には剣術の他流試合免許を柿沼村の四分一道場(昭文館)より受け、自宅に剣術道場「鉄心館」を開設、その後熊谷町、吹上村に分館を開設しました。また、熊谷・鴻巣警察署の剣術嘱託教師を引き受けるなど、門弟300余人を育てた。
明治31年に創立直後の「熊谷製糸株式会社」経営を引き受け社長となり、ユニークな経営で会社は発展し、大正7年に10割配当2期の高配当を行い株主を優待しました。繭は契約養蚕者を募り、指導者を派遣して、蚕品種の統一、飼育指導による均一した良繭の安定的確保を図りました。
大正14年、熊谷大火で工場を焼失しますが、かねてより計画していた吹上分工場を急遽建設するとともに、石原に7千坪の本社工場を再建しました。昭和5年社長職を娘婿の舞原諶一(1883-1953)に譲り引退しています。
大正14年、熊谷大火で工場を焼失しますが、かねてより計画していた吹上分工場を急遽建設するとともに、石原に7千坪の本社工場を再建しました。昭和5年社長職を娘婿の舞原諶一(1883-1953)に譲り引退しています。
また、明治39年から昭和8年まで忍商業銀行吹上出張所所長を務めています。
政治家としては、明治36年から大正13年まで、吉見村会議員、明治36年から44年まで大里郡会議員、大正7年吉見村村長に就任しています。
大正11年には、小八林地内の逆コの字型に迂回していた明神坂を、私費を投じて1560坪を買収して寄附し、直線道を完成させた。この事績を伝えるために、同地に「大明神坂開鑿碑」が造立されています(写真右)。
大正11年には、小八林地内の逆コの字型に迂回していた明神坂を、私費を投じて1560坪を買収して寄附し、直線道を完成させた。この事績を伝えるために、同地に「大明神坂開鑿碑」が造立されています(写真右)。
晩年は、東京まで南画を習いに通い、雁画を好んで描きました。
息子は、㈱埼玉銀行代表取締役頭取、会長、相談役を歴任し、経済界で活躍した長島恭介(1901-1992)。
写真左は、昭和初年の石原工場操糸工場の内部。女性が、煮た繭玉から糸を撚り合わせ、中央の糸車に巻き取らせる操糸作業を行っています。
【参考文献】
2024 岡田辰男 「気骨の人、長島甚助の多彩な生涯」『熊谷郷土文化会誌』第77号
【参考文献】
2024 岡田辰男 「気骨の人、長島甚助の多彩な生涯」『熊谷郷土文化会誌』第77号

昭和初年の石原操糸工場の内部

大明神坂開鑿碑