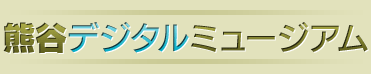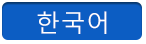代島久兵衛(だいじまきゅうべえ)

代島久兵衛墓碑
江戸時代の和算家代島久兵衛を紹介します。
久兵衛は、安永8年(1779)、大里郡大幡村代に生まれました。諱は亮長、通称久兵衛。富田姓ですが、代村東善寺の山号である代島を名乗っています。
幼少より算術を好み、はじめ佐倉藩で算術を学び、後、上州板鼻の小野栄重の門弟となりました。
奈良村・玉井村・大麻生村の三堰の図を作り忍侯に献じています。また、算術に長けていることから、奈良村の吉田市右衛門宗敏より、備前渠仁手堰の工事設計、丁場割等の監督を依頼されました。
天保7年(1836)「武州大里郡大麻生村絵図面」を門弟鈴木仙蔵、藤井安次郎と製作、弘化4年(1847)代村の諏訪神社に、極小極大の問題を解いた算額を奉納しており、熊谷市指定文化財に指定されています。
門弟は500人に及び、鈴木仙蔵、明野栄章、納見平五郎、嶋田角三郎などがいます。
文久3年(1863)85歳で没す。元治元年(1864)、生家の近くに墓碑が建てられています。施主代島萬次郎、発願主:藤井源兵衛、鈴木仙蔵、高田甚之丞、横倉弥右衛門、島田角次郎、明野信右衛門。
参考文献
- 『熊谷人物事典』日下部朝一郎 昭和57年 国書刊行会
- 『北武蔵の和算家』山口正義 平成30年 まつやま書房